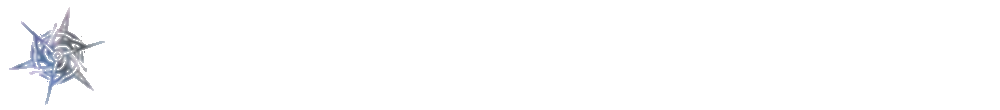治葛 静音
やかつ しずね
こんな可愛い子、放っておけないでしょ?
ほらほら、助けさせてあげてもいーわよ!
嬉しければ笑い、悲しければ泣く。怒られれば落ち込むが、翌日にはけろっと忘れてしまっている程単純――治葛静音は、どこにでもいる平々凡々な少女だ。彼女がもし、母親に捨てられなければ。復活の日の贄として選ばれなければ。母親が男と蒸発してしまった事実を知ってはいるが、それを理由に全てを諦める程物分かりが良いわけではなく、悲しみを曝け出せる程素直な性格もしていない。来るその日への恐怖を笑顔の下にひた隠しにし、明るく振る舞うことだけが現在出来る唯一の抵抗だ。何度も壁の外へ逃亡を謀ってはその度に失敗しており、それでも諦めない不屈の精神が他者にどう映っていようとどこ吹く風。もう一度外の世界に出て母に会いたいと、ただそれだけを願っている。
優しく穏やかな母が豹変したのは、5年前に父が他界したことがきっかけだった。はじめこそ一人で娘を育てようと必死になっていたが、次第に弱っていく心は男に救いを求めるようになり、邪魔者となった静音は半ば捨てられるようにしてXに引き渡された。「いつか迎えに来るから」という言葉が嘘だと見抜けない程愚鈍ではないが、優しかった母への希望を捨てられないのも事実。“いつか”が現実となることを願い、起きる筈もない奇跡を今日も待ち続けている。
やだちょっとやめてよ馬鹿!どこ触ってんの!?離しなさいよこの変態ッ、いくらあたしが可愛いからってどさくさに紛れて変なことしようって言うんじゃ……あいたッ!(Xの領地内に似つかわしくない、ぎゃんぎゃんと騒ぎ立てる声が響き渡るのは何もこれが初めてではなかった。数年前に半ば強制的にこの場所に連れて来られて以降、治葛が脱走に挑んだのは最早両手では数えきれない程の回数に上るから。外出を許された信徒が外に出るのと同時に飛び出してしまおうという正面突破の脱走劇は、此度も当たり前みたいに失敗に終わる。結果信徒の男に担がれ連れ戻された治葛は、ぽいと自室に放り投げられた。まるで荷物を扱うようなその粗雑な素振りに「タンスの角に小指ぶつけろクソ!!」「手元狂って眉毛全部剃り落とせ!!」と思いつく限りの罵倒を浴びせるが、その一切合切は無視され男は部屋から出て行ってしまった。)は、腹立つぅ~…!あたしの言葉なんて聞く価値もないっての!?オイコラ待ちなさいよ、アンタらにとっちゃ大切な大切な生贄サマでしょうが!?もっと丁寧に扱えー!(閉ざされた扉に向かってクッションを投げつけるのと、――「静音ちゃん、怖くないの?」問いかけられるのは、殆ど同時だった。同室の少女から投げかけられた問に、ぱちりと瞬きを零したのも一瞬。答えは当然決まりきっているから、)怖くないわよ、あんな空っぽの奴ら。(答えることに迷いはない。ここにいる人間は、全員空っぽだ。存在もしない“教祖様”とやらを信じて、訪れる筈もない救いを求めている。自分を持たない相手など怖くない――怖がってたまるか、と言った方が正しいのかもしれないけれど、そうした本音は喉の奥にぐっと飲み込んだ。張りぼての虚勢の裏に隠した本音はどうやら見破られずに済んだらしく、部屋の隅で膝を抱えた少女は小さく言葉を続ける。すごいな、私は怖いよ。死ぬのが怖い。誰にも助けてもらえないのが怖い。明日どうなるか分からないのも、全部怖い。――紡がれる言葉に耳を傾けながら、心臓が訴える鈍痛を誤魔化すように握り締めた拳に力を込める。爪の先がてのひらに食い込む感覚に痛みを覚えても、力を緩めようとはしなかった。少女が紡ぐ言葉は、全部全部、治葛にとっての本音でもあった。)……あたしは、(微かに震えた唇をちいさく開いて、結局言葉を紡ぐことはなく、はくりと空気を食べる。)……あたしは、あんな奴らにびびったりしないから!ほらっ、アンタもめそめそすんのはやめる!泣いてる暇があったら、次の脱出計画考えるわよ!待ってなさいよ、次はとびきりすごい計画を考えてみせるから。外に出たら何をしたいかでも考えてるといいわ、……あたしはそうね。とびきりでっかいパフェが食べたい!フルーツいっぱい乗ったやつ!(言って部屋を飛び出し、我武者羅に領地内を駆けて行く。途中で信徒達ともすれ違ったけれど、向けられる視線全てを振り払うようにして人気のない場所まで走って走って、それから空を見上げた。手を伸ばせば、すぐに雲にだって手が届きそうなのに。外と内を阻む白く高い壁が、今日も途方もない絶望を伴って立ちはだかる。あの壁の向こうで、母はどんな顔をして生きているのだろうか。――胸裏に浮かんだ母の顔は、もう輪郭すら曖昧になるほど朧気だ。忘れたくないという気持ちに反して薄れ行く記憶に目の奥が熱を持つけれど、そうした痛みを振り払うようにしてぎゅっと目を閉じた。どんなに恐怖を感じても、絶望に呑まれそうになっても、涙は流さないと決めたから。それはこの身以外に何ひとつ武器を持たぬ女の、たった一つの矜持だった。)