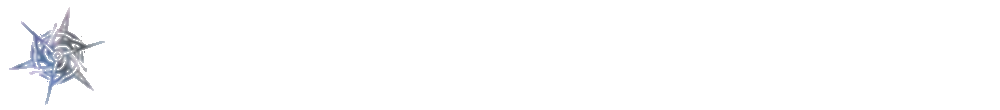立花 蓮
たちばな れん
僕は嘘つき。でも君を助けに来たのは本当。
さあ、おいで。光の当たるところへ。
立花蓮は、二級昇格に意欲的ではない。単独任務が発生するからだ。元々自堕落的で自分に甘く、サボるためなら嘘だって平気でつくし他人を騙すことも厭わない。術式を駆使して逃げ回ることだってザラである。そんな立花の鬼門が”五条悟”だ。術式の開示より先に本質を見破られたのは彼が初めてで、それがなくとも命の恩人である。高専に入学して以後のらくら四級に甘んじていた立花でも、彼が前に出てきた今回の話は頷かざるを得なかった。出来れば弱いままでいたい、身の丈以上のことなどしたくない。けれど光の差さぬ場所などないと証明するためならば、一筋の光に自分もなれる気がした。
光を操る術式。屈折率を操作し全く違う姿に見せたり、そこに居ないように見せたりすることが出来る「浄玻璃」は潜入調査などに重宝されている。また、自身の呪力を光に変じさせる「火輪」は出力次第で相手の目をも灼く威力となるが、同級生らからはもっぱら便利な懐中電灯扱いである。この二つの能力ゆえに立花が前線に立つことはほとんどないが、【陽炎】の真骨頂は周囲の光と自身の呪力を練り合わせ光線として発する「摩利支天」にある。その威力は容易く人の頭蓋も貫き焦がすけれど、相当な呪力と集中力を必要とするため乱発は出来ない。
しょうがないだろ。五条先生に言われたんだ。(ムッスリとした膨れっ面で同級の揶揄を睥睨する。緩めにデザインされた詰め襟を引っ張って口元まで隠しても、立花の不機嫌は隠せぬものだろう。――東京都立呪術高等専門学校二年・立花蓮は、特級呪術師・”五条悟”の名において二級呪術師への昇級に臨む。まだまだ四級で甘い汁をすすっていたかったが、流石にいつまでも”五条悟”は放っておいちゃくれないようだ。主な実績を補助要員として積み上げてきた立花をいきなり二級に推すというのも彼らしい。授業も終わった放課後、帰り支度を片手間に整えながら、はあ、とわざとらしく零す溜息は重たい諦観として落ちてゆく。)……五条先生に頭が上がらない理由? ああ~~……まあ、よくある話だよ。命の恩人。(級友が首を傾げるのもさもあろう。立花は五条に甘い。学生らに粗雑な扱いをされる五条を庇ったり、共に逃げたりなんぞザラである。日下部や夜蛾ではこうはいかない。今回の二級推薦だって、五条以外なら「やだ」の一言で蹴っただろう自信もある。なぜ、とは当然の疑問だ。級友から視線を外して、教室の窓から山奥の雄大な自然を眺めた。なんてことない、よくある話。立花の家は稀に呪術師を輩出する家だ。御三家のような伝統の術式はなく、本当に突然変異のように生まれる。立花蓮はそれだった。幼少の頃より【陽炎】を使うことが出来た立花は、努力が嫌いな子どもだった。夏休みの宿題に手をつけたことなんて一度もないし、教科書を読んで書き写すだけの授業に意味を見いだせなかった。すぐに行方をくらます立花に、周囲の大人は匙を投げる。これ幸いとサボり癖が悪化した中学時代、卒業間際のとある日のこと。)なんでなんでなんで……ッ!!(桜の蕾がはちきれんばかりだったはずの明るい校舎は、今や怨嗟の渦に飲まれている。そこかしこで生徒や教師の阿鼻叫喚が木霊し、場所によっては窓が割れ鉄骨がむき出しになっていた。突然呪霊が襲って来たのだ。後にオカルト部が良くない儀式をしたらしいとは話に聞いたが、逃げ回るのが精一杯だったこの時の立花には知る由もない。高専に行くことは決まっていた。呪力、術式などの基礎知識もある程度頭に詰め込まされた。だが戦闘経験はない。特にこの頃、立花自身も【陽炎】はサポート特化の術式だと認識しており、出来る攻撃は『火輪』の出力上げのみ。それも大人数がいる校舎では使えない。最低限注意を引きながら、縺れる足で逃げる。時折肩から床に転け落ちながら、そのたび腕で体を持ち上げてまた逃げる。反撃の機を見いだせぬまま、少しでも光のあるほうへ。陽光を遮るものがない校庭にやってきたのは立花にしては道理で、すがらに校舎を巻き込まぬよう帳を下ろす。他の呪術師が騒動に気付くまで、ひとりで立ち回らねばならない。息が上がる、頭が真っ白だ。)こんなところで、死ねない……!(ゴーグルを下ろして臨戦態勢を取る。特注の遮光レンズは『火輪』の最大出力からも目を守ってくれるスグレモノ。ただしその場合、立花自身も全身の火傷を覚悟しなければならない。『浄玻璃』で行方を晦ましたように見せかけ、飛び退き距離を取る。右手の手のひらを上に向ければ、光の球体が徐々に大きくなってゆくだろう。)『かり――ッ!! ガ……ハッ(しかし技を発動させるより先に呪霊の攻撃で体がふっ飛ばされる。『浄玻璃』はあくまでフェイク、”いないように見せる”だけで実際には”そこにいる”。見破られたのか単なるまぐれか、攻撃が当たってさえしまえばダメージを免れるものではない。ホームベース裏のフェンスがなければ校舎に激突していただろう、はがれるように地に落ちた立花への追撃をしない呪霊ではなかった。やられる――そう思った瞬間に、今度は呪霊がホームランのように吹き飛んでゆくではないか。立ち上がりながらもあっけに取られた立花が状況を理解するより先に、突然隣に現れた怪しい目隠しの男が肩を叩いて囁く。「集中して」「周りの光も自分の呪力も全部細い糸にして、あいつに放つんだ」。ひどく怪しい男なのに、すんなりイメージが出来てしまった。センターの向こう側から、呪霊が再度こちらへ向かってきている。男と二人、真っ直ぐに呪霊を見ていた。背中が痛い、怖い、逃げ出したい。謎の男に任せて駆け出したい。けれどそれより強く、光の糸のイメージが脳内で主張して暴れまわっていた。まるで蜷局のようだ。「来るよ」必死で糸を解く。他のことを考える余裕はない。呪霊がセカンドを超えた。「引きつけて」ほつれが少しずつシンプルな線になって、ゆるやかなたわみを見せ始める。僕は今息をしているんだろうか。わからない。ホームベースを蹴った呪霊がこちらへ手をのばす。「今だ」糸になった光の束がピンと張ったその瞬間――”それ”は、呪霊の脳天を貫いていた。ハッ、ハッ、ハッ、ようやく呼吸をしていたことを思い出すと同時に、立花は意識を手放したのだった。)――その後はスパルタ。『摩利支天』の為になんかめっちゃややこしい数学の勉強させられるし。僕より僕の術式に詳しいんだよ、あの先生。(雑巾を絞った汁を吐き出すような顔をして五条悟との初対面を語る立花の声音には、けれど確かな親愛や信頼が滲んでいただろう。あの時の恩はきっと死ぬまで返しきれやしないし、立花が戦えるようになっていることを一番知っている人物でもある。ポリポリと頭を掻きながら級友と寮への道を辿ろう。いまさら逃げられやしないのだ、”五条悟”からは。それは立花もそうだし、「奪還しろ」と言われた囚われのお姫様にもいえることだろう。)……助けられるなら、助けてやんなくちゃな。(級友と別れて戻ってきた寮の自室には、閉ざされた遮光カーテンの隙間から鋭い西日が差し込んでいた。所以は知らない、興味もない。けれど光が差す余地があるのなら。必死になって手を伸ばすのも悪いもんじゃない――柄にもなくそんなふうに思いながら、ベッドに沈もう。あの日のことは、思い出すとひどく疲れるんだ。)