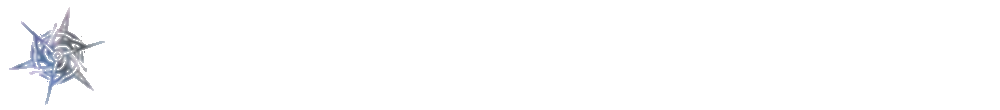梵 一期
そよぎ いちご
ねえ、ほんとにあたしってしあわせもの?
こんなの、パパだって笑ってくれないよ。
矛盾だらけの感情は、思春期特有のものだと周囲は言う。壁の抜け穴を探しているのに、見つけたくない。狂ってしまった母親なんて捨てて父親の元へ行きたいのに、繋いだ手を離せない。死ぬのは怖いのに、贄に選ばれることを望んでいる。華美な頭髪や服装は年齢を加味されてまだギリギリお小言で済まされてきた。異質な鳥籠の中での生活は長い方だからこその甘い目もあるかもしれない。不安定にゆらめきながらも、同世代の教徒たちとは良好な友人関係を築く快活な剽軽者だ。新顔を積極的に輪へ引き込もうとする社交性も持ち合わせているが、融通の利かないところもある。こんな環境下でなければ、どこにでもいる平凡な少女であっただろうに。
母の発言が要領の得ないものに変わったと幼心に感じた折、世界も180度変わってしまった。当時創設間もなかったらしいXに入信した母は所謂古株というやつで、だからといって権力があるでもないが、取り分け敬虔な教徒である。反対を唱えた父と引き離される形で、いつか贄に選ばれますようにとの母の願いを一心に受けて壁の中へ連れてこられた。狂気を孕む空気に怯えて、反発して、逃げ道を探して、それでもかつてのやさしい母の面影を忘れられず殊勝にも期待に応えようと囚われ続けている。
(見上げる空は仄白んできれいなはずなのに、ひどく淀んでいるみたいだ。取り分け冷え込む朝一番。郵便物を管理する部屋を訪れるのは、この鳥籠のような世界にやって来てからの日課となっていた。一日として欠かさず出し続けた父宛の手紙はきっと一度も検問を通ったことなどないのだろう。冷たい廊下を歩む素足の先があおく変色し始めている。心まで冷えていく思いだ。したためた内容は他愛ない世間話で、あのテレビ番組がおもしろかった、だとか、あのアーティストの曲が好き、だとか、限られた娯楽から拾ったものしかないのに、宛先だけで弾かれてしまうのだと一期は悟っていた。それでも、もしも――。あわい期待を捨てきれない矛盾にため息をつくと、ふわりと白い息が舞った。)これ、おねがいね。(簡素な言葉で一通の封筒を渡すと、当番の教徒はまたかとでも言いたげに眉尻を落とした。やれやれ――そんな声が聞こえるようだったものだから、むっとしてしまったのは条件反射のようなもの。)ねえ、あたし宛のきてない?(ぶすっと吐き捨てるような問いには変わらず否を示されるだけ。半年程前までは、父の他にもうひとり宛先があった。取り寄せた雑誌には古風にも読者が文通相手を募集する投稿欄があって、その中のひとりに賭けたのである。無事検問をくぐり抜けて、幾度かやり取りを重ねたけれど、それもぷつりと途絶えてしまった。こちらかあちらか、分からないけれど弾かれたのだろうと一期は思う。諦めてしまえば楽なのに、感情をコントロールするというのは随分と難しい。)――あ。あんた、昨日きた子でしょ? これからごはんなら一緒にいこ。(乱雑にドアを閉めて部屋を後にすると、ひとりの少女と鉢合わせた。かろい誘いを投げたつもりでも、不機嫌が尾を引いて、ややぶっきらぼうな声色になったことを内省する。それにしても、不安に染まる顔ばせはあまりにも見ていられないもので、まるで一期の爪先のような色をしていたから、思わず取った手をさするように撫ぜてやる。少女は恐らく年上であろうが、着飾って背伸びした一期のことは年下には思われなかったかもしれない。)気分じゃなくてもなんか食べといたほうがいいよ。その顔ならおかゆとかおじやとか、言えば用意してくれるかもだ。あたしはね、朝は白いパンにマーマーレードのジャムを塗って、ソーセージと、半熟の目玉焼きを食べるのがすきよ。だからそうだった日は目一杯元気に暴れまわってやることにしてるの。ここはあんたにとっていい場所じゃなかったとしても、そういう楽しみをひとつくらい見つけときなよ。(うふふ。息を吹きかけるみたいに笑声を漏らす姿は明るく元気な平凡な少女のそれであったろう。足の爪先はそろそろ感覚がぼやけてくるくらいまっさおになっていたけれど、繋いだ手はぬくい温度を分け合って、連れ立って歩く少女の顔色も幾らかマシに映った。彼女もいつか母のように変わってしまうのだろうか。すべてを諦めて、瞳の光を失ってしまうのだろうか。たとえどうなろうとも、一期はここで生きる限り、友人としてこうして彼女の手を取り続けるだろう。反感を覚えながらも、母にそうし続けているのと同様に。)