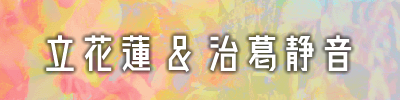治葛静音〆 ♦ 2021/02/18(Thu) 18:42[85]
嘘、ついて欲しかったの。(帰って来ると言って欲しかった。待っていてと言って欲しかった。呪いでもなんでもいい。彼が残してくれるものがひとつでもあるのなら、それを光として生きていけるから。けれど渋谷が夜に包まれたその翌日、彼は帰って来なかった。その次も、その次の日も。漸く得たのは、生死不明というあまりにも曖味な情報だけだ。彼をはじめ五条悟や夜蛾学長以外に高専に伝手などない女は、彼の情報をそれ以上得ることは叶わなかった。高専に逃げるようにと言われていたが、状況があまりにも変わり過ぎているがゆえにそれも断念。最早あの場所は今、学園として機能などしていないのだろう。魔窟と化した渋谷に親子の居場所はなかったから、母とふたりで遠縁の親戚を頼って逃げるように田舎に出たのは2018年11月半ばのこと。あの日彼が家に招いてくれていなければ、母も自分も死んでいただろう。また命を救われたのに、ありがとうすら言えない日々が胸裏を締めつけ息苦しさを訴える。彼の母との縁も次第に希薄になっていき、連絡を取れなくなってしまったのはさていつのことだっただろう。)……意地悪だよね。嘘つきって自分で言ってたくせに、結局あたしには嘘なんてついてくれなかったんだから。蓮が「帰ってくるよ」って言ってくれたら、あたしずーーーっと待ってあげられたのに!(枕元に飾ったパンダに向かって、静かに語り掛ける夜。当然返事はない。塗装も随分剥げたパンダは黒かった片耳だって白くなってしまっていて、流れた月日を否が応でも感じ取ってしまう。わかっている。嘘をつかなかったことが、彼の優しさなのだろう。この身を縛ることがないようにと、そう願ってくれていたに違いない。ならば、自分のするべきことは何だろう。)……ちゃんと、前向かなきゃ……。(ぐす、と鼻を鳴らして小さく零した。いつまでも縛られることがないようにと、小さな決意をひとり胸裏に打ち立てる。彼の願ってくれかもしれない通りに生きたかった。幸せにならなきゃ。"いい子"にならなきゃ。だってこの命は、彼がくれたものだ。)
(田舎での生活は、順風満帆だとは言い難かった。東京と離れたとはいえど、不安定な日本。どのような影響があったかは知れない。あと少しで卒業だった大学も、休校扱いになってしまっている。Xを共に過ごした少女達の中には医者になった者だっていると聞いていたし、順当に行けは他の面々だって新たな人生の分岐点に立っている頃合いだろうか。社会に出るのがまた先延ばしになるのだとため息を零しながらの母との二人暮らし、もう暫くはアルバイトで日々の生計を成り立てる日が続きそうだ。彼の生死が分からなくなって、もう一年が経つ。たかが一年、されど一年。長い人生の中で見れば瞬く間に過ぎ去る日々だろうが、便りも何もない空白は今後を考えるには十分過ぎる時間だったろう。彼を思い出さない日はない。涙に暮れる夜だってある。けれど日は確かに過ぎていき、日常の中で笑うことだって増えたのは薄情だろうか。バイト先の飲食店に頻繁に訪れる青年に、好きなんだと告白されたのはこの頃だった。食事に行った。ふたりで出かけた。手を繋いだ。触れた指先は優しくて暖かくて、生きた人間の温度を感じさせてくれる。嘘などひとつもつかない、優しい人だった。この人なら好きになれるかもと願って逢瀬を重ね、一歩踏み出そうとしたその矢先。誘われた動物園で、 気づいてしまった。パンダの尻尾って、白いんだね。何気なく隣に並ぶ彼から投けかけられた一言に、一瞬で脳裏に愛しい記憶が翻る。外の世界に、彼が連れ出してくれた日のこと。初めてふたりで出かけた大都会。好き勝手に買った洋服よりも、彼がくれたキーホルダーの方がずっとずっと嬉しかったこと。世界中にひとりぼっちになってしまったような寂しさから、彼が救い出してくれたこと。すぐに逃げ出すと言うくせに、いつだって誰かのために戦い続けている姿がいっとう好きだったこと。今もまだ、彼が好きで好きでたまらないこと。)ふえ……、っ(一度思い出せば、もう駄目だった。前を向こうなんていい子ぶった思考は瞬く間に霧散して、涙がぼろぼろと溢れ出す。隣に並ぶ青年に、涙と嗚咽の間に何度も繰り返した。ごめんなさい、ありがとう、貴方のことは大好きだけど、もっともっと大好きな人がいるの。忘れられないの。その人じゃないと駄目なの。)蓮が好きなの、 これからも。蓮じゃなきゃ駄目なの……。
お母さーん、おかえり。晩ごはん出来てるよー。(──月日は巡る。ひととせ過ぎて、また秋がやって来る。少し離れた場所に広がる田園は、すっかり黄金色に一面が塗り替えられていた。肩まで切った髪を撫でる風も、いつの間にか稲穂の香りを纏わせている。彼の母に弟子入りを果たすことは今日に至るまで終ぞ叶っていないが、それでも包丁を扱う手は随分と慣れたものになった。)田島くんとこのお母さんがね、お家でたくさん穫れたからどうぞってくれたの。おいしそうでしょ?(言って、テーブルの上に並ぶ食事を指さした。生徒の親から野菜をもらうことは多く、他に並んだ白菜の煮びたしだってその恩恵に肖ったものである。醤油と砂糖だけで炊いたシンプルなかぼちゃの煮つけは、深い橙色をしてうっすらと湯気を漂わせていた。上手になったねと笑う母に、 柔く双眸を細めてみせる。 蓮に食べさせてあげたいねって、そんな言葉は静かに胸の奥へと飲み込んだ。未だ、その後の便りはない。呪い蔓延る呪術界、彼の行く末を知る者はいるだろうか。それすらも曖昧なまま、女は今日も生きている。おかえりって。頑張ったねって言える日を、ずっとずっと待っている。"いい子" でなんていられない。わがままでいていいのだと、これも彼が教えてくれたことだ。だから女は、彼を諦めることを諦めた。月に叢雲花に風。さよならだけが人生なんて、絶対言わせてなるものか。)